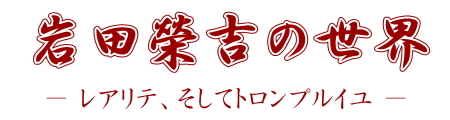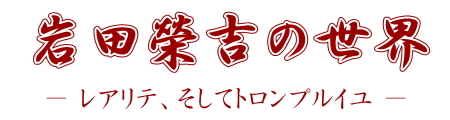岩田榮吉の作品
作品点描
魔女(その2《ランプと魔女》)
大きな時代の変わり目には、分裂する秩序の間隙から思ってもみなかった人間社会の深層が露出するのでしょうか。16世紀から17世紀ころのヨーロッパ各地で集団的妄想から生れた「魔女」は、理性重視の懐疑主義、科学的合理主義の浸透とともに絶滅したかに見えました。しかしそれは表面を覆う薄皮のようなものであったことがわかります。逼塞していた「魔女」はやはり大きな時代の変わり目に姿を現します。
岩田の《ランプと魔女》(画集No.29)は6号という小品ながら、再び姿を現した「魔女」「魔女狩り」が主題です。画面中央に大きく描かれる石油ランプは、1880年代以降フランスで広く使われた量産実用品の「ランプピジョン」(
作品点描~ランプのモチーフ(その1) 参照)。その火は既に消えていて、ガラスのホヤには室外からの光が差し込む窓と、キャンバスに向かう赤いセーターの岩田自身が映っています。
20世紀に現れた「魔女」「魔女狩り」の筆頭に挙げられるのは、無論のこと「ホロコースト」です。反ユダヤの感情はヨーロッパに古代から認められますが、第1次大戦後のドイツでは、過大な賠償負担、極端なインフレ、政情の不安定等々直面するあらゆる災禍の根源がユダヤ系の人々にあるといった集団的妄想から、なんら拘束力ある法令もなく、主管する閣僚も官庁もなく、予算もないままに、600万人以上もの生命が犠牲になったと言われます。
《ランプと魔女》は細部まで描き込まれ、密度高い仕上がりです。しかしながら岩田は、この主題でこれ以上の展開を試みていません。人間社会の基層に潜む同根の事象は、人種差別からごく身近にみられるイジメまで、今日でも随所に顕現しています。岩田は重いテーマを回避したのではなく、対処困難な課題に直面したとき絶望の代わりに人間が頼るべきものは何かを、あらためて自身に問いなおそうとしたのではないでしょうか。
 《ランプと魔女》 1970年 (画集No.29)
《ランプと魔女》 1970年 (画集No.29)